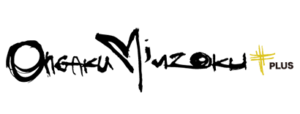【八重山の唄者】第11回 具志堅 郁子
具志堅 郁子 (ぐしけん いくこ)
生まれ年:1956年生まれ
出身地:竹富町西表大原
在住地:石垣市登野城
所属:八重山古典音楽安室流協和会/琉球古典音楽野村流保存会
研究所名:具志堅郁子研究所
平成9年 (1997年) 11月琉球古典芸能コンクール琉球舞踊 新人賞
平成11年(1999年)11月八重山古典音楽コンクール 新人賞受賞
平成12年(2000年)10月八重山古典音楽コンクール 優秀賞受賞
平成12年(2000年)11月琉球古典芸能コンクール琉球舞踊 優秀賞受賞
平成15年(2003年)10月八重山古典音楽コンクール 最高賞受賞
平成15年(2003年)12月琉球古典芸能コンクール琉球舞踊 最高賞受賞
平成17年(2005年)2月八重山古典音楽安室流協和会 教師免許取得
平成17年(2005年)11月沖縄タイムス芸術選賞琉球古典音楽三線新人賞
平成18年(2006年)9月玉城流翔節会琉球舞踊 教師免許取得
平成19年(2007年)11月沖縄タイムス社芸術選賞琉球古典音楽三線優秀賞
平成20年(2008年)9月とぅばらーま大会歌唱の部 最優秀賞受賞
平成21年(2009年)11月沖縄タイムス社芸術選賞琉球古典音楽三線最高賞
平成26年(2014年)4月玉城流翔節会琉球舞踊 師範免許取得
令和2年(2020年)琉球古典音楽野村流保存会教師免許取得
令和6年(2024年)八重山古典音楽安室流協和会 師範免許取得
 Q1. 出身地はどちらですか?
Q1. 出身地はどちらですか?
竹富町西表大原出身です。女4名に一番下が男1名の5人姉弟の3番目の三女です。ひと昔の時代なので一番下の長男が産まれるまで両親は頑張ったみたいです(笑)。父が船乗りだったので、大原と石垣を行き来していて、母が自宅で旅館業をしていました。
Q2.幼少の頃は?
父が船乗りだったので大原と石垣の両方にも家がありました。一番下の弟が小学校入学、私が小学6年生になるタイミングに、大原の家を引き払い一家で石垣の登野城の方へ引っ越ししました。なので、小学6年生になる4月に大原小学校から登野城小学校に転校しました。
Q3. 幼少の頃の地域行事への参加などはいかがでしたか?
大原では、地域の豊年祭や奉納行事は、普通に眺めているだけだったかもしれません。とはいえ、小さな村なので、近所のオバーのお祝いなどは、みんなで集まって踊りの練習などして、余興などはしていました。ウチの父が新城島出身で三線も弾いていたし、母は竹富出身で踊りが好きでした。家に三線も置いてあり、民宿もしていたので、家ではいつも民謡が流れていたので私たち姉妹は小さい頃からずっと両親二人の歌や踊りをみて育ちました。
 当時、「フォーシスターズ」という民謡を歌う4人組の人気女性グループが居たのですが、それを父が面白がって、私たち4姉妹に真似させて、上の2人の姉には三線持たせ、三女の私には太鼓を、四女はタンバリンとか持たせたりして「パナリ・ワラバーズ」と名前を付けて(笑)色んなお祝いの余興の場に出演させられていました。ウチの4姉妹は、八重山民謡というよりは、ラジオから流れて来る聴き馴染みのある沖縄民謡や歌謡曲を演奏することが多かったですね。私が小さい頃は、西表大原には映画もテレビも無い時代に、親子ラジオから聴こえてくる沖縄の芸人さんたち照屋林助さんなどが島の公民館に演奏しに来てくれていたのです。すごくそのステージが楽しみでした。
当時、「フォーシスターズ」という民謡を歌う4人組の人気女性グループが居たのですが、それを父が面白がって、私たち4姉妹に真似させて、上の2人の姉には三線持たせ、三女の私には太鼓を、四女はタンバリンとか持たせたりして「パナリ・ワラバーズ」と名前を付けて(笑)色んなお祝いの余興の場に出演させられていました。ウチの4姉妹は、八重山民謡というよりは、ラジオから流れて来る聴き馴染みのある沖縄民謡や歌謡曲を演奏することが多かったですね。私が小さい頃は、西表大原には映画もテレビも無い時代に、親子ラジオから聴こえてくる沖縄の芸人さんたち照屋林助さんなどが島の公民館に演奏しに来てくれていたのです。すごくそのステージが楽しみでした。
私の場合は、父からでなく一番上のお姉さんから三線を教えられていました。なので、遊びの延長でなんとなく三線も弄っている、というレベルでした。
Q4.4姉妹でステージに立つのは楽しかったですか?
実は、すごい恥ずかしがり屋で、イヤイヤでステージに上がっていました。父に“させられた”感じでした(笑)。その中でも長女だけは楽しんでいたかも。一番上の姉さんは小さい頃から三線の音が聴こえると走って見に行く子だったそうです。私も、歌は好きでしたが、人前に出ることが得意ではなかったですね。それでも担当している太鼓を石垣島の竹富島出身の幸本先生のところに父の船で通って習っていましたし、父に言われて、色んなところに「パナリ・ワラバーズ」として4姉妹で民謡ショーをしていました。
 Q4. 本格的に三線を弾くようになったのは?
Q4. 本格的に三線を弾くようになったのは?
嫁いだ先の義母も野村流で三線をしていたそうで、家にも三線や琴がありました。一人の時間に、工工四など見ながら独学で三線を弾いて聴き覚えで勝手に歌っていました。実は、私は唄三線よりも舞踊を始めるのが先でした。竹富島出身の私の母が、新井ミチ先生の研究所で八重山舞踊をしていて、時々発表会に呼ばれ、踊りを手伝うこともありました。もちろん入門するよう誘われましたが、まだ子供も生まれたばかりで、舞踊研究所に入ることは出来なかったです。息子が高校生になり子育てもひと段落した頃に、琉舞を習いたくて、平田弘子先生の研究所に入門しました。その流れで、野村流保存会の三線研究所にも入門しました。母のお手伝いの踊りや、地域の婦人会などの踊りに参加する中、色々な八重山舞踊を踊る中で、八重山民謡の唄三線にも興味が出てきて、丁度、親戚で従弟の黒島聡(安室流協和会)が、三線の先生をしていたので平成9,10年頃に彼の研究所に下の妹と一緒に通うことになりました。でも実際に琉球古典・八重山民謡の唄三線を習ってみると、それまでの勝手な解釈で歌っているところも沢山あることに気づき、改めて細かな歌唱などを学びました。平成11年(1999年)八重山古典音楽協会新人賞を、翌年の平成12年(2000年)に優秀賞を、平成15年に最高賞を頂きました。教師免許を平成17年2月に頂いて、平成20年にとぅばらーま大会で最優秀賞を頂きました。
 Q5. 今一番メインで使われてる三線について。
Q5. 今一番メインで使われてる三線について。
今、メインで使用している三線は、亡くなった私の親父から、本格的に三線を始めた頃に、下の妹の分も含めて、新しい三線を作ってくれてプレゼントしてもらいました。それまでは、具志堅家にあった三線を使わせてもらっていました。
Q6. 思い出のステージはありますか?
ステージの思い出は“失敗”の思い出しかないです(笑)。私、本当にあがり症なんです。とぅばらーまチャンピオンになった後、太陽の里で歌って欲しいと依頼が来て、ステージで演奏始めたのに、歌詞がまったく出てこなくて(笑)。ずっと伴奏が続けて、その時、(黒島)聡が笛吹いてくれていたのですが、聡の傍まで寄っていて、小声で「歌詞なんだった?」と聞いてやっと歌い始めたという大失態をやらかしました(笑)。とにかく、人前で歌う時は緊張してしまうのです。コンクールも本当に苦手で、声がうわずったりして声が上手く出せなかったりはしょっちゅうありましたね。
Q7.そんな中、とぅばらーま大会に出場されていたんですよね?
4姉妹で出場したいなぁと思って、みんなに声をかけたのですがイヤだと断られてしまって(笑)。あがり症とは別に、「とぅばらーま」は素敵な唄なので歌いたいという気持ちが強くて。「とぅばらーま」は座席に座って歌う民謡とは違って、野に出てウァーと声を出すでしょ。自分の気持ちを思いっきり声に出す。私の親父は新城島出身、小さい頃から、新城島の豊年祭に連れていかれて私も参加していました。新城島の豊年祭では、“アカマター”“クロマター”が出てきて集まったみんな一晩中大声で歌い合うのですが、それがとても楽しくて。毎年、豊年祭に参加するのが楽しみでした。大きい声で歌うところがトゥバラーマと通じているように感じたりして。あがり症の自分にとってステージでの独唱は厳しいだろうと思いましたがあえて挑戦してみようと思ったのです。残念ながら姉妹で私一人だけ、すでにとぅばらーまチャンピオンだった(黒島)聡に、お願いして練習を始めました。それから2,3年後の平成20年(2008年)に初めて挑戦した大会でチャンピオンになれました。この時の大会は台風の影響で、新栄公園の野外ステージではなくて、市民会館大ホールのステージで行われたんですけど予選会の時はとても上手く歌えたのですが、本番はやはりあがり症の部分が出てしまい、自分的にはあまり上手く歌えなかったです。それでも、チャンピオンにして頂けて本当に光栄でした。

Q7. 郁子先生の好きな曲は?
やっぱり「とぅばらーま」になりますかね。「月ぬまぴろま節」も好きかな。
Q8. 最後に郁子先生にとって八重山の謡(うた)とは?
私にとって謡は、やはり無くてはならいモノ、歌っていない自分は想像できないですね。もちろん、歌うことで日ごろのストレス解消でもあるし(笑)。やはり、新城島の豊年祭や西表大原の巻き踊りなど、思いっきり声を出すことが私の原点なので、三線持った節唄でも、身体から思いっきり声を出さないと歌った気にならないんですよ(笑)。

平成20年 正月特番で共演したフォーシスターズの皆さんとの記念写真(本人提供)